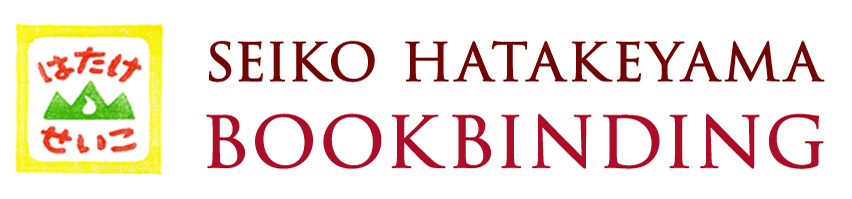溝付け板
溝付け板
ファルカタ集成材をMDF版画板で挟み、側面に両面テープでステンレス板を取り付け。いずれきちんとしたものを作ろうと思いながら、問題なく使えるので、そのまま使用。
上からステンレス板2mm厚/板150mm×225mm、ステンレス板2.5mm厚/板150mm×225mm、ステンレス板3mm厚/板225mm×300mm厚。
耳出し板
耳出し板
左:一番初めに試しに作った耳出し板。机のひきだしに眠っていた古いプラスチック定規(30cm)を再利用。定規の斜め部分をやすりで鋭角にし、板ぎれの端をカンナで斜めに削り、両面テープではりつけ。二本の定規は別メーカーで形状が違うため、厚紙などで調節。A7判、B7判用。
中央:コクヨ方眼直線定規使用。A7判、B7判用。
右:アクリルショップはざいやにて、6mm厚アクリル押出板、(残り板厚1mmのため)5mmテーパー加工指定で購入。やすりで鋭角にして、MDF版画板にはりつけ。A5判用。
製本プレス機 小
製本プレス機 小
ステンレス寸切平先ボルトM16はフリマで安く購入。長さが少し違うのでナットの位置で調節。取り外し可能なクランクハンドル角穴、30度台形ねじM16、30度台形ねじ用ナットはミスミで購入。角フランジ形ユニット、ゴム脚はモノタロウで購入。ナット、ワッシャー、板等、廃材再利用。板の幅136mm長さ460mm。A5判までプレス可能。
製本プレス機 大
製本プレス機 大
クランクハンドル角穴、30度台形ねじM16、30度台形ねじ用ナット、ステンレスシャフト、リニアブッシュはミスミで購入。角フランジ形ユニットはモノタロウで購入。タモ集成材はヤフオクで。板の幅300mm長さ486mm。B4判までプレス可能。
刻印打ち機
刻印打ち機
打ち棒つきの刻印は、位置決めが難しいので、打ち棒の取り外しができる刻印やタイトル用。ラウンドモウルで打刻後、使用。垂直でなく、微妙に斜めになっているので、四方向に角度を変えて打つ手間がかかるものの、刻印はきれいで問題なし。ヒシ目打ちに利用する場合は一発で簡単に穴をあけることができる。ドリルチャックはモノタロウ、トグルクランプはミスミで購入。ステンレス寸切荒先ボルトが長すぎるのは、廃材を再利用しているため。
簡易かがり台(本かがり用)組み立て前
簡易かがり台(本かがり用)組み立て後
簡易かがり台(本かがり用)組み立て
簡易かがり台(本かがり用)
試作品。組み立て式。がたつきがあるものの、それなりに使えるものだから、いつものようにそのまま利用。そのうちきちんとしたかがり台を作り直す予定。

簡易製本プレス機1

簡易製本プレス機2

簡易製本プレス機3

簡易製本プレス機4

簡易製本プレス機5

簡易製本プレス機6
簡易製本プレス機
本のサイズに応じて、プレス、やすりがけ、パラがけなどに使う。
ロメラ(背表紙用木型)
ロメラ(背表紙用木型)
表紙の背の丸みを形づくる道具。竹を半分に割り、やすりがけで滑らかにして、二枚の板ぎれで固定。が、ヌメ革だと、表(吟面)に響くため使用できず。へり磨き棒はクラフト社。
コツと金槌
コツと金槌
左:丸み出しに使うコツ。やすりをかけてなめらかにした木ぎれ。
右:SK11ステンレス両口玄能、須佐製作所ステンレス武力屋槌、製本用金槌。製本用金槌は鉄製のため、サビで本文背が汚れるので、丸み出しや耳出しにはステンレス金槌を使用。長い柄を切って短くしてある。
グルーバーと版画刀と革漉き包丁
グルーバーと版画刀と革漉き包丁
漉き歴が浅いので、研ぎが下手。裏研ぎする必要があることも知らず。砥石で研いでも、すぐ切れなくなるので、下段の革砥で切れ味をアップさせる。感想文シリーズは使用革のサイズ(横600mm×縦248mm)が大きいので、漉きに時間がかかる。
革砥と青棒
革砥と青棒
板ぎれに革床をはりつけ、椿油を垂らして青棒ですりこむ。これで革漉き包丁を研ぐと、切れ味が増す。革漉きには欠かせない。
刻印
刻印
クラフト社、協進エル、IVAN、SN Stamp、MorandoTools等。アルミダイキャストの刻印は安いが、不良品が多く、精度も低い。コーティングが剥がれたりなど耐久性も低い。よく使う刻印は、高いが、真鍮やステンレス製がよい。刻印によっては、刻印するヌメ革の厚みが2mm以上でないと、満足できる結果が得られないことがあるので、表紙に使う薄い革には使えないことも。
タイトル刻印図案
タイトル刻印
タイトル刻印
デザインした刻印を、ルーターで削ろうと思ったものの、木を削る版画と違って、真鍮は飛び散るわ、繊細なフォントはもちろん削れないわ、早々に無理だとあきらめ、26engraveにて制作してもらう。フォントの周囲に余白があるので位置決めに苦労し、悲しいかな位置がずれたりするが、きれいに刻印できる。職人さんに感謝。表紙の背に刻印する場合、空押しのため、丸背だと革が伸びるので、刻印が薄くなる。打ち棒を取り付けてラウンドモウルで打刻後、打ち棒をはずして、刻印打ち機で何度も刻印すると、タイトルがくっきりして満足が得られる。
ラウンドモウル
ラウンドモウル
木槌は肘を痛めるので危険。ラウンドモウルだと力を入れなくても刻印が打てるので、肘痛もない。
ステンレス定規等
ステンレス定規等
止型スコヤ、曲がり尺、溝付けに使うステンレス板など。
筆
筆
油彩筆豚毛。正麩糊塗り用とニカワ塗り用。
趣味で本を作っている手製本作家です。製本用道具は手に入りにくく、販売していても高価なので、使いやすいように自分で作るしかありません。廃材等を再利用した自作の道具、特にプレス機は、なにぶん素人なので、不格好で、適当で、部品の使い方等、間違っているかもしれません。